霞が関跡

場所:霞が関2丁目1先 地下鉄霞ヶ関駅A2出口前歩道
霞が関は、奥州街道の関門で武蔵国(現在の東京都・埼玉県・神奈川県の一部)にあったと伝えられています。その場所は西に高台があり、東に水辺を望むといわれますが、正確な場所は分かっていません。江戸時代には、武家屋敷が立ち並び、武家屋敷の場所を示す通称地名として使われました。明治時代になり、東京府の町名として正式に決定されています。
江戸時代の霞が関跡周辺
江戸城やその周辺の様子、行事や装束を豊富な挿絵と共に解説した『徳川盛世録』(明治22年)に描かれた「紅葉山参詣之図」には、桜田門から霞が関に続く大名屋敷が描かれています。
現在、「霞が関跡」の標柱が建っている場所には広島県浅野家の上屋敷、霞が関坂を挟んだ道の向うには福岡藩黒田家の上屋敷(現在の外務省の位置)がありました。

『徳川盛世録』に描かれた大名屋敷と「霞が関跡」周辺。

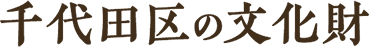
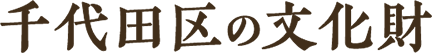






更新日:2022年10月03日